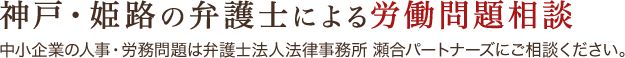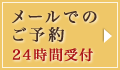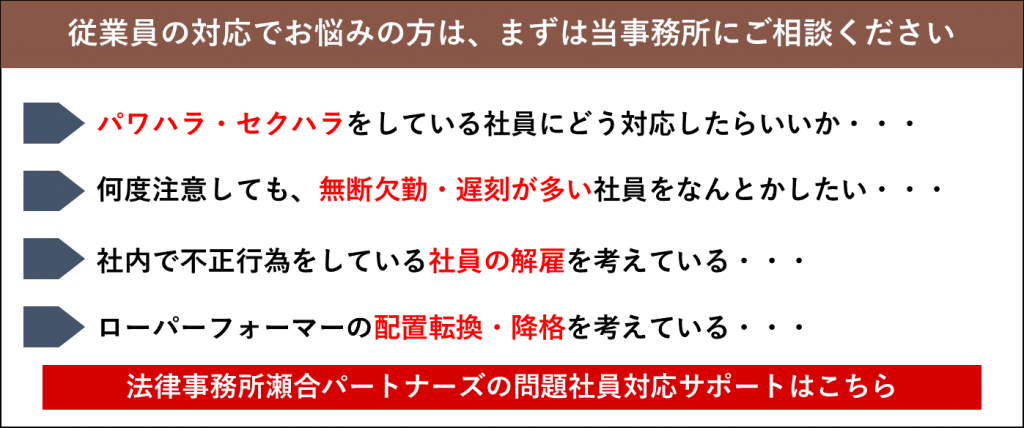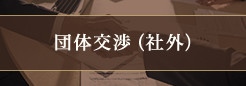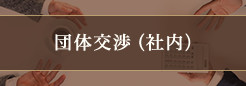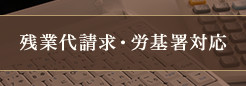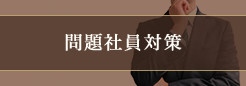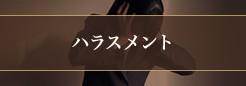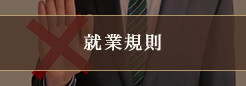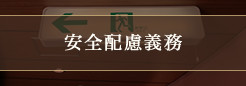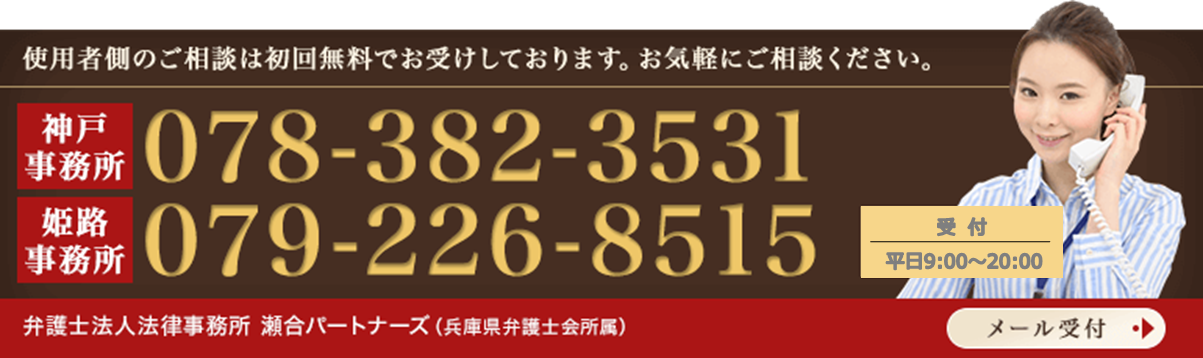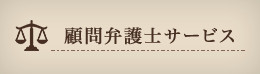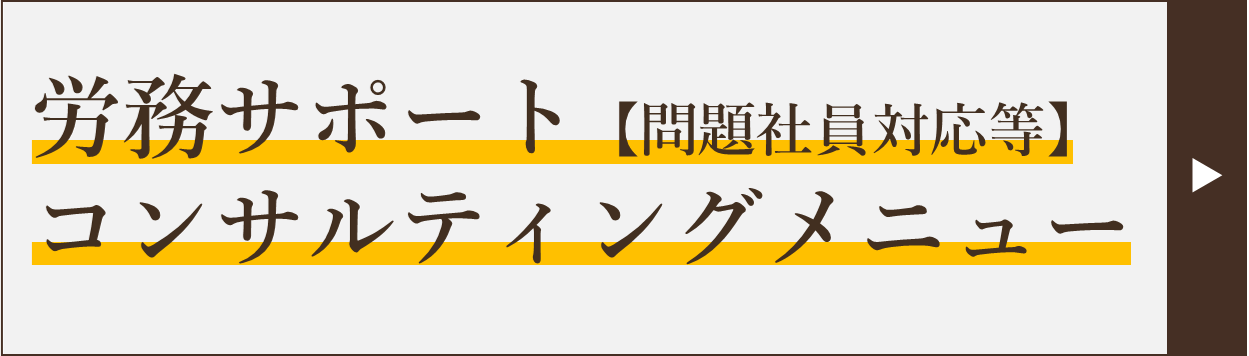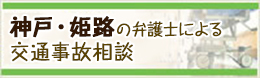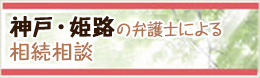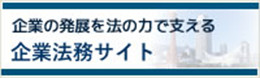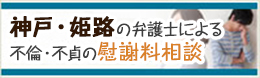労使協定と過半数代表者の選出手続における注意点
1 はじめに
近年、労使協定を締結する際の過半数代表者の選出手続を不適法とし、労使協定を無効と判断するといった、裁判例が増えています。そこで、過半数代表者を選出する際の注意点について、説明したいと思います。
2 労使協定の意義
(1)労基法は、その定める労働条件の基準は最低のものであり、この基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分は無効となります(これを「最低基準性」といいます)。また、労基法が定める基準は、基本的に、すべての使用者がその雇用するすべての労働者に対して一律に守らなければならないとされています(これを「一律性」といいます)。
(2)もっとも、上記労基法の規制には、民主的手続による規制の分権化・柔軟化から、次のような例外が認められています。
すなわち、事業場の労働者の過半数を組織する労働組合がある場合にはその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者との書面による協定(いわゆる「労使協定」)によって、その協定の範囲内で労基法の規制を免れることができます(もう一つの例外として「労使委員会」もありますが、ここでは実務でよく利用されている労使協定のみを扱います)。
3 過半数代表者の選出
(1) 労使協定を締結する労働者側当事者
当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合がある場合には、当該労働組合が労使協定を締結する労働者側の当事者となります。そのため、これとは別に過半数代表者を選出してもその過半数代表者と労使協定を締結することはできません。
そこで、当該事業場に労働者の過半数を組織する労働組合がない場合に、当該事業場の労働者の過半数を代表する者として選出された過半数代表者が、労使協定を締結する労働者側の当事者となります。
(2) 過半数代表者の要件
この過半数代表者の要件としては、手続の民主制を保障するため、①「過半数代表者は管理監督者であってはならないこと」、②「法が規定する過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法(労働者の話合い、持ち回り決議等を含む)によって選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」が必要となり、これらの要件を満たしていない労使協定は無効となります。
4 選出にあたっての注意点
(1) 使用者の意向に基づき選出された
上記のとおり、過半数代表者の要件の一つとして、「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」が求められます(労基則6条の2)。
「使用者の意向に基づき選出された」とは、使用者が直接代表者を指名した場合だけでなく、使用者が候補者を推薦するなど候補者の選定に関与した場合も含まれます。
もっとも、使用者は過半数代表者が法所定の事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければなりません(労基則6条の2第4項)。そこで、使用者が選挙の発意・告示や選挙の管理を行うなど選出手続に形式的に関与することは、具体的な候補者や代表者の選定に関与しない限り「使用者の意向に基づき選出された」場合にはあたりません。
(2) 当該事業者の労働者以外の者の選出の可否
適正な手続を保障する観点から、当該事業場の労働者の意見や実情を反映する必要があります。そのため、当該事業場の労働者以外の者については、当該事業場の過半数代表者になり得ないものと解されています。
(3) 過半数代表者の選出であることを明確にして実施されたものであること
過半数代表者を選出する手続は、その旨を明確にして実施されたものでなければなりません。この点、著名な判例として、トーコロ事件(最二小判平成13年6月22日)があります。同判例は、従業員の親睦団体の代表者が自動的に労働者代表となって締結された36協定の効力を否定しました。
(4) 期間ごとの選出手続の実施
労使協定に期間の定めがある場合には、その期間ごとに適法な選出手続が実施される必要があります。
この点、十数年前に1年単位の変形労働時間制を採用した際に過半数代表者を選出する話合いがもたれた後は、選出の話合いがなされないまま同人が労使協定を締結していた事案で、民主的手続がとられていないことから、同労使協定の効力を否定した判例があります(堀口労政行政事務所事件・釧路地帯広支判令和5年6月2日)。
(5) 不投票を有効投票による決定に委ねる(又は賛成とする)取扱いの適法性
過半数代表を投票で決定する際に、投票しなかった者を有効投票による決定に委ねるとする(又は賛成とする)取扱いをした場合、その適法性も問題となります。
この点、労基法上の原則の例外を設けるという法的効果の重大さ、および投票率が低い場合に少数者の指示により過半数代表者が選出されてしまう可能性があることを考えると、過半数の労働者の積極的な意思表示により支持されることが必要であるとする見解が参考になります(水町勇一郎著「詳解労働法第4版」東京大学出版会121頁参照)。
なお、この点について、選出を支持していることが明確になる民主的手続がとられているとは認められないとして、専門業務型裁量労働制を定める労使協定の効力を否定した判例として、学校法人松山大学ほか事件(松山地判令和5年12月20日)があります。
(6) すべての労働者を選出手続に参加させること
過半数代表者の選出においては、当該事業場のすべての労働者に選出手続に参加する権利を保障する必要があります。
例えば、当該事業場の正社員が、全労働者の多数を占めるからといって、その他の社員には手続の参加を認めないといった場合は、手続に重大な瑕疵があるものとして、過半数代表の選出が無効となるおそれがあります。
(7) 任期制の可否
この点、争いはありますが、民主制の確保と過半数代表者の機能強化を図ることの重要性のバランスから、少なくとも1年以内の任期を設定し過半数代表者として行う活動を具体的に明示して民主的に代表者が選出された場合であれば、選出時に明示された活動を過半数による支持をその都度確認することなく任期期間中に行うことを認めるべきであるとする見解が参考になります(水町勇一郎著「詳解労働法第4版」東京大学出版会124頁参照/逆にいうと、選出時に明示されていなかった活動については、過半数による支持をその都度確認する必要があります)。
(8) 代表者の人数
この点、争いはありますが、多様な労働者層の意見を反映させることの重要性から、正社員の代表1名と契約社員の代表1名がいずれも当該事業場の労働者全体の過半数の支持を得て選出され、連名で労使協定を締結する等、労働者の過半数の支持を受けて選出された複数の代表者が共同して活動することも可能とする見解が参考になります(水町勇一郎著「詳解労働法第4版」東京大学出版会124頁参照)。
(9) 過半数代表者が適法に選出されたことを明らかにする証拠の保存
何よりも重要なこととして、あとで問題となった場合に備えて、過半数代表者が適法に選出されたことがわかる証拠を残しておく必要があります。
上記証拠がないことから、労使協定の効力を否定された判例として、乙山色彩工房事件(京都地判平成29年4月27日)やナルシマ事件(東京地判令和3年10月14日)があります。
5 法改正の動き
過半数代表制度については、過半数代表者の適正選出を確保し、過半数代表制度の基盤強化を図る必要があることから、現在、厚生労働省の「労働基準関係法研究会」報告書(2025年公表)に基づき、労基法法改正等を行うことが検討されていますので、注視していく必要があります。
6 まとめ
このように、労使協定の過半数代表制度については、その有効性を巡り注意しなければならない点が多くあります。また、専門型裁量労働制を採用する法人に対する未払残業代請求などの事案において、この点が主な争点となることも予想されます。
そのため、労使協定の過半数代表を選任する場合には、これらの点にご留意ください。なお、当事務所では、会社側の労務事件に関するご相談、ご依頼も多数取り扱っておりますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
本記事は2025年10月8日作成時点での記事となります。
【参考文献】水町勇一郎著「詳解労働法第4版」東京大学出版会 118頁~126頁