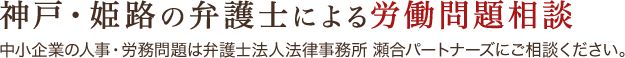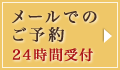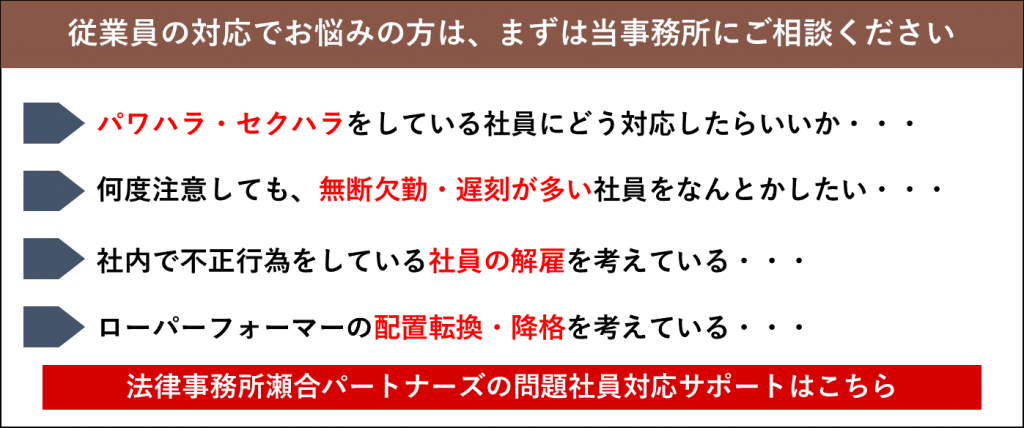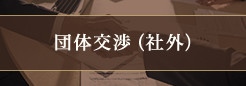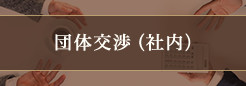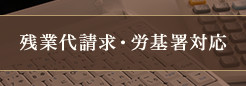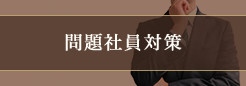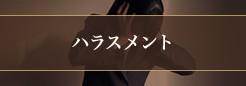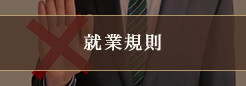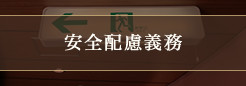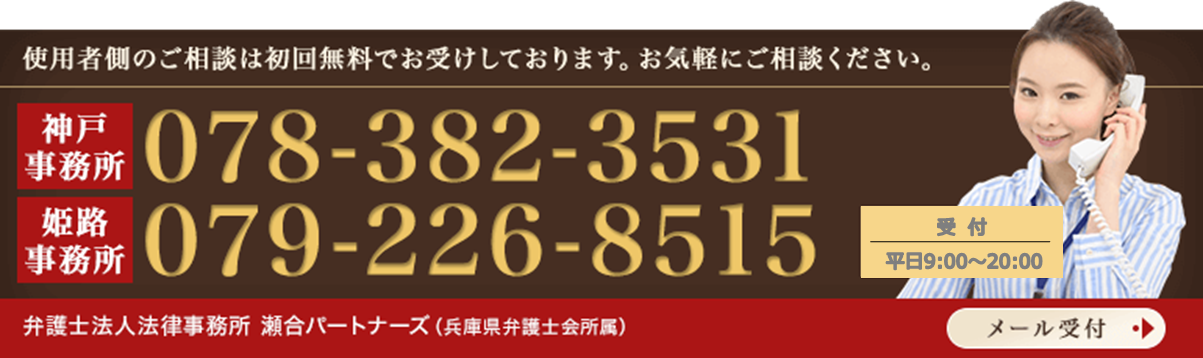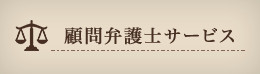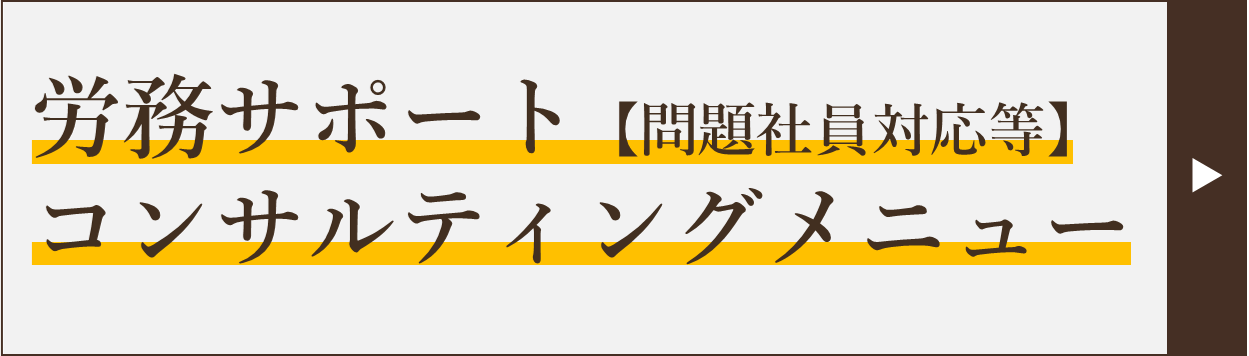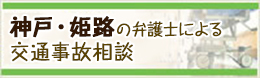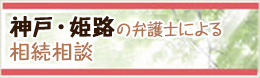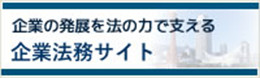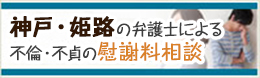2025年育児介護休業法改正について
1.改正育児介護休業法とは?
2025年に改正された育児・介護休業法は、「育児・介護と仕事の両立を支える制度の強化」と「企業の義務の拡大」が主な柱となっています。背景には、少子高齢化の進行と、仕事と家庭の両立支援の必要性があり、これまで努力義務や任意であった制度の一部が義務化され、従業員への周知や意向確認などの具体的行動も求められるようになりました。改正の主要ポイントは、以下の点になります。
(1) 男性育休取得率の公表義務の拡大
常時雇用する労働者が1000人を超える企業に対し、男性労働者の育休取得状況などを年1回公表することが義務化されていましたが、今回の改正により対象となる企業が、300人を超える企業まで拡大されます。
(2) 子の看護休暇の対象拡大
看護休暇の対象となる範囲が、小学校3年生修了まで拡大され、看護休暇取得事由も、新たに①感染症に伴う学級閉鎖等、②入学式、卒園式が追加されました。
(3) 残業免除の対象拡大
残業免除が請求可能となる労働者の範囲が、3歳未満の子を養育する労働者から、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大されます。
(4) 短時間勤務制度の代替措置にテレワーク導入
改正前においても、3歳未満の子どもを持つ労働者が短時間勤務を希望すれば、企業側は勤務時間を6時間まで短縮しなければならず、短時間勤務を認めることが難しい場合代替措置を講ずる必要がありますが、今回の改正で新たに代替措置としてテレワークが追加されました。
(5) テレワークの導入
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じる努力義務があります。
また、要介護状態の家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じる努力義務があります。
(6) 介護離職防止措置の義務化
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、①研修の実施、②相談窓口の設置、③制度利用事例の収集・提供、④制度利用促進に関する方針の周知、のいずれかの措置を講じなくてはなりません。
(7) 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
介護に直面した旨の申し出があった労働者に対して介護休業制度等に関する事項の周知と利用の意向確認等を、個別に行わなくてはなりません。
(8) 柔軟な働き方を実現するための措置等
企業は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、①~⑤の措置の中から2つ以上の措置を選択して講じる必要があり、労働者は、2つ以上の措置の中から1つを選択して利用することができます。
①始業時刻等の変更
②テレワーク等
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ養育することを容易にするための休暇の付与
⑤短時間勤務制度
(9) 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
企業は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項について、労働者の意向を個別に聴取したうえで、自社の状況に応じて配慮しなくてはなりません。
2.実務上の影響と企業への影響
改正により、企業は次のような新たな対応が求められます。
• 社員への制度説明と意向聴取の義務(育児・介護ともに)
• 勤務時間短縮やテレワーク、休暇の新制度導入
• 就業規則・育児介護休業規程の見直し
• 社内研修の実施や相談体制の整備
特にテレワークや時差出勤など、従来の勤務形態を柔軟に変更できる制度の整備が重要です。制度があるだけでなく、「従業員が選べる状態」にしておく必要があります。これにより、企業には、以下のような影響が及ぶことが想定されます。
• 人事・労務部門の負担増加(周知・聴取・記録義務)
• 働き方改革への対応が進まない企業には人材確保の面で不利
• 対応が不十分な場合、労基署や労働者からの指摘リスク
3.対象企業の規模とスケジュール
改正内容について、対象となる企業と施行日をまとめると以下のようになります。
| 改正内容 | 対象企業 | 施行日 |
| ⑴男性育休取得率の公表義務 | 従業員数 300人超 | 2025年4月1日 |
| ⑵子の看護休暇の対象拡大 ~ ⑺介護離職防止のための個別の 周知・意向確認等 |
全企業 | 2025年4月1日 |
| ⑻柔軟な働き方を実現するための 措置等 ⑼仕事と育児の両立に関する個別 の意向聴取・配慮 |
全企業 | 2025年10月1日 |
4.弁護士を活用して整備すべきポイント
企業法務に精通した弁護士の関与により、改正対応を効率的かつ法的リスクを抑えて進めることが可能です。以下のような場面では、特に弁護士の関与が有効です。
(1) 就業規則・規程改定
• 法改正に基づく文言の見直し
• 育児・介護関連規程の明確化(対象年齢、取得手続、代替措置など)
(2) テレワーク・短時間勤務制度の導入設計
• 不公平が生じない制度設計
• 企業の裁量を残した運用設計
(3) 男性育休取得率公表義務への対応
• 公表の対象・方法の確認と記録整備
• 不適切な公表による名誉毀損・風評リスクの対応
(4) 労使トラブル予防
• 育児・介護に関する不利益取り扱いの回避
• 休業・制度利用を理由とする不当解雇・嫌がらせの防止指導
5.まとめ
2025年の改正育児・介護休業法は、「両立支援の実効性確保」がキーワードです。制度があっても活用されなければ意味がなく、企業には「使わせる工夫」や「丁寧な対応」が求められます。
対応を怠ると、行政指導や労使紛争のリスクも高まります。
就業規則の改定、制度設計、社内研修など、あらゆる場面で法的な観点からの対応が不可欠であり、弁護士のサポートを受けることで、負担を軽減しつつ適正な運用が可能となります。企業としては、単なる法令順守にとどまらず、働きやすい職場づくりの一環として、主体的に取り組む姿勢が今後の競争力にも直結するといえるでしょう。
以上