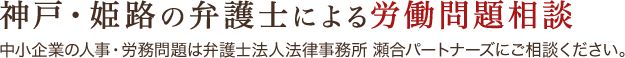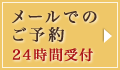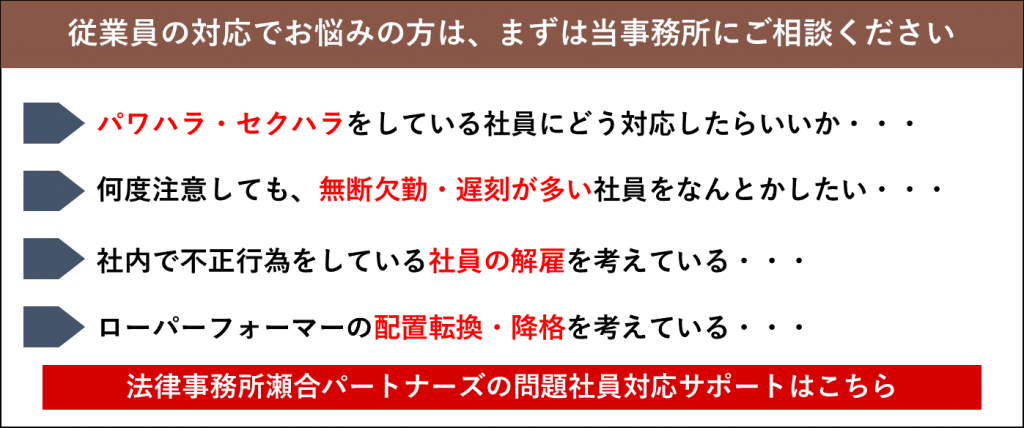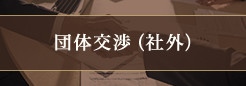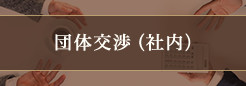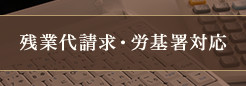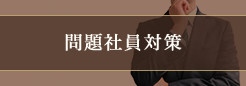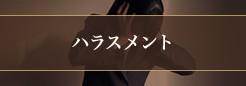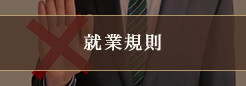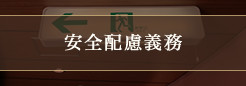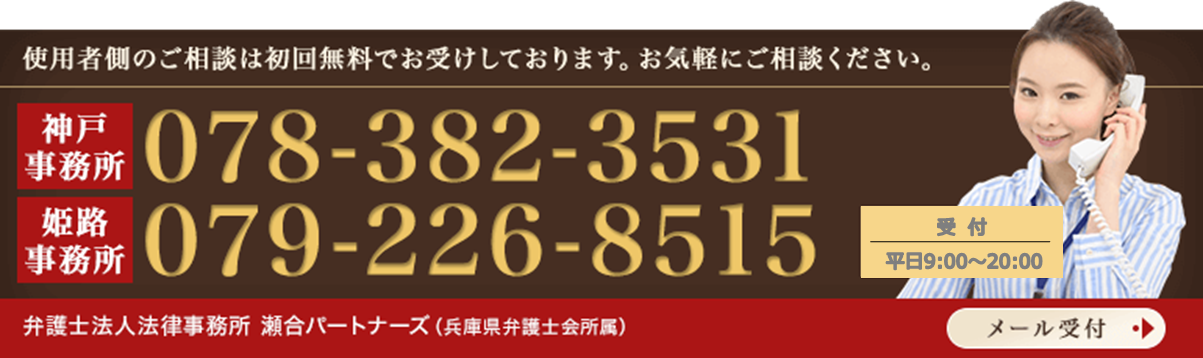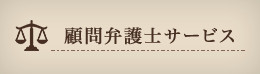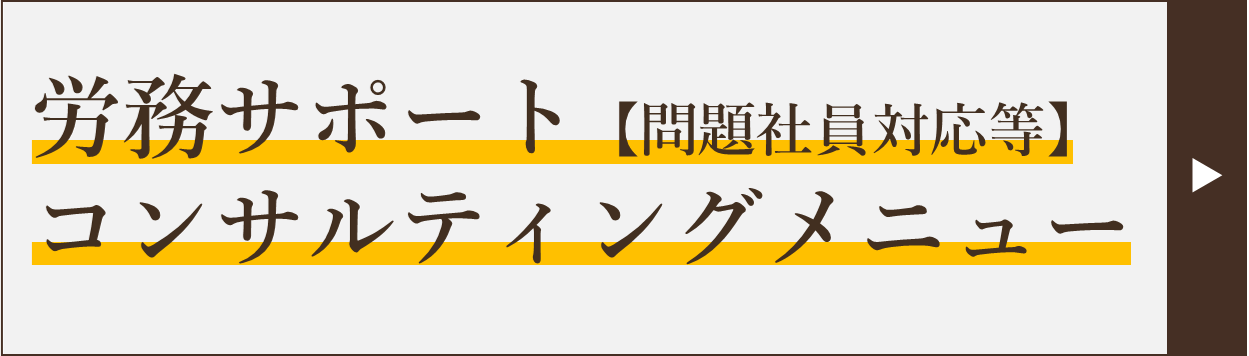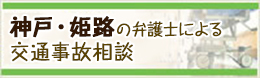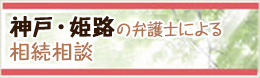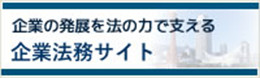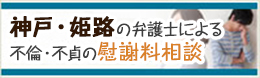社会保険労務士が気を付けるべき広告規制・景品表示法
1 はじめに
私たちの生活には、日々さまざまな広告があふれています。
しかし、その中には、実際よりも優れて見せたり、有利に見せたりする誤解を招く表現も存在します。こうした不当な表示から消費者を守り、公正な競争を維持するために設けられているのが不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)です。この法律は、「虚偽・誇大な広告によって、消費者の合理的な選択が妨げられること」を防止することを目的としています。
また、景品表示法だけでなく各業界にも広告規制は存在し、社労士業界にも職業倫理上の広告規制が存在します。
以下では、景品表示法をはじめとした社労士が気をつけるべき広告規制について、ご説明します。
2 景品表示法の基本構造
(1)3つの類型
景品表示法で規制される不当表示は、以下の3つの類型になります。
・優良誤認表示:実際より著しく優れていると誤認させる表示
・有利誤認表示:価格や条件が実際より有利だと誤認させる表示
・指定告示に係る表示:特定分野(不動産、原産国、ステマ等)の不当表示
(2)優良誤認表示
優良誤認表示とは、以下の要件を満たす表示になります。
①内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示
又は
内容について、事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって
② 不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ
合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示
「著しく」優良と誤認させるかは、社会通念上許される程度を超えたものといえるかが基準となります。その誤認がなければ、顧客が誘引されることが通常ないであろう程度に至っていた場合、「著しく」優良と誤認させたとして優良誤認表示となります。
具体的には、以下のような表示が優良誤認表示となります。
・「カシミヤ100%」→ 実際には50%
・「大学合格実績No.1」→ 実際には他社と比較したことはない
・「この技術を使った商品は当社だけ」→ 他社も同技術を採用
消費者庁長官は、優良誤認表示か否かを判断するために必要であると認めるときは、事業者に対し15日間の期間を定め表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めることができます。事業者が合理的根拠資料を提出できない場合、「不実証広告」として優良誤認表示とみなされます。
(3)有利誤認表示
有利誤認表示とは、以下の要件を満たす表示になります。
①取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
又は
取引条件について、競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって
②不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示
具体的には、以下のような表示が有利誤認表示となります。
・「通常価格から1000円引き!」→ 通常価格で販売した実績がない
・「今だけ半額!」→ 実際には同条件のセールを何度も継続している
(4)指定告示に係る表示
指定告示に係る表示とは、内閣総理大臣が不当表示として指定している表示です。以下の7つが指定されています。
・無果汁の清涼飲料類等についての表示
・商品の原産国に関する不当な表示
・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
・不動産のおとり広告に関する表示
・おとり広告に関する表示
・優良老人ホームに関する不当な表示
・一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステルスマーケティング)
ステルスマーケティングとは、広告主が自らの広告であることを隠したまま行う広告です。2023年10月から、新たに不当表示規制の対象になりました。
規制の要件は、以下の2つです。
①事業者が自己の供給する商品・サービスの取引について行う表示であり、
②一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの
例えば、事業者から商品の広告を依頼されてSNSに商品についての投稿を行ったにもかかわらず、「#PR」を大量のハッシュタグの中に紛れ込ませたり、動画内で一瞬だけ「広告」と表示するだけでは、事業者による広告と判別できないため、ステルスマーケティングと判断される可能性があります。
3 違反時の措置・罰則
景表法違反が認められると、以下のような行政処分や刑事罰の対象となります。
行政処分 :措置命令・課徴金納付命令
刑事罰 :100万円以下の罰金(法人は3億円以下)
民事リスク :適格消費者団体による差止・返金請求
景表法違反の疑いのある行為をした事業者に、自主的に是正措置計画を申請してもらう代わりに、その計画が認定されたときは、行政処分を免除する「確約手続」も導入されており、行政処分を免れる可能性もあります。
4 社労士業界の広告規制
社会保険労務士法(以下「法」といいます。)には、第1条に社労士の使命、第1条の2に社労士の職責が定められており、社労士の職業倫理が規定されています。全国社会保険労務士会連合会は、「不適切と考えられる情報発信に関する指導指針」を2025年1月に改正し、社労士が職業倫理に背く不適切な情報発信をしないように規制しています。つまり、社労士には、職業倫理上の広告規制が存在しているのです。
具体的には、以下の広告は職業倫理上不適切とされています。
・問題社員は、うつ病に罹患させて退職に追い込みましょう!
・労働時間を変えずに、残業代だけを大幅削減する方法を教えます!
・合法的に社会保険料を節約する方法はこちら
・厚生労働省のモデル就業規則をそのまま使うと労働者の思うつぼですよ
・〇〇助成金獲得のノウハウ教えます。成功報酬は支給額の〇%です!
・100%会社側に立って労働者と戦います!
・監督署の調査に対抗できます!
5 まとめ
広告や表示の規制は、一般消費者を守るためのルールであると同時に、事業者にとって「信頼を守るためのルール」でもあります。景品表示法や業界指針を正しく理解し、誇張や誤認を避けた誠実な情報発信を行うことが、結果的に事務所の信用と顧客満足度を高めることにつながります。
以上