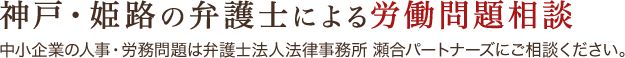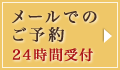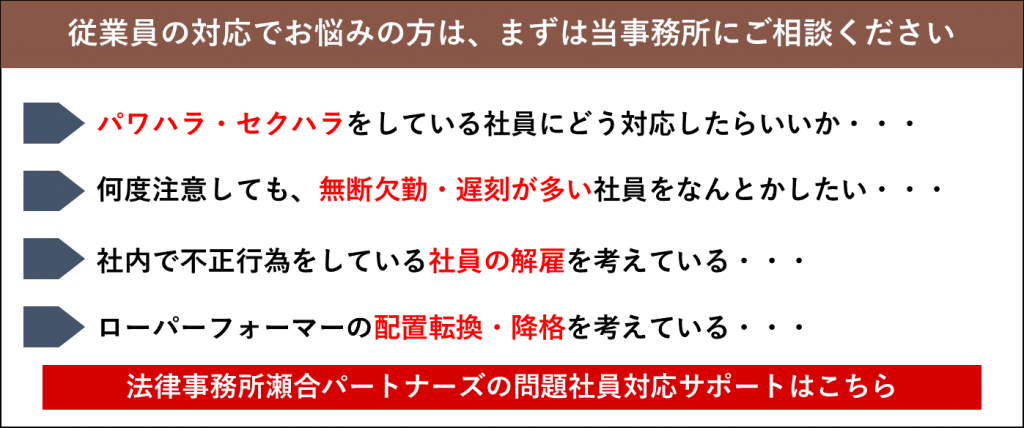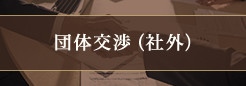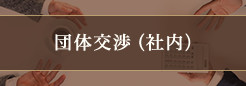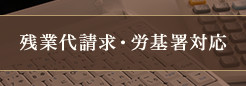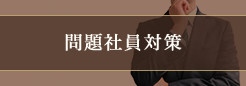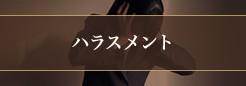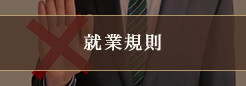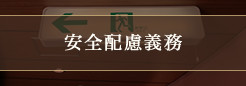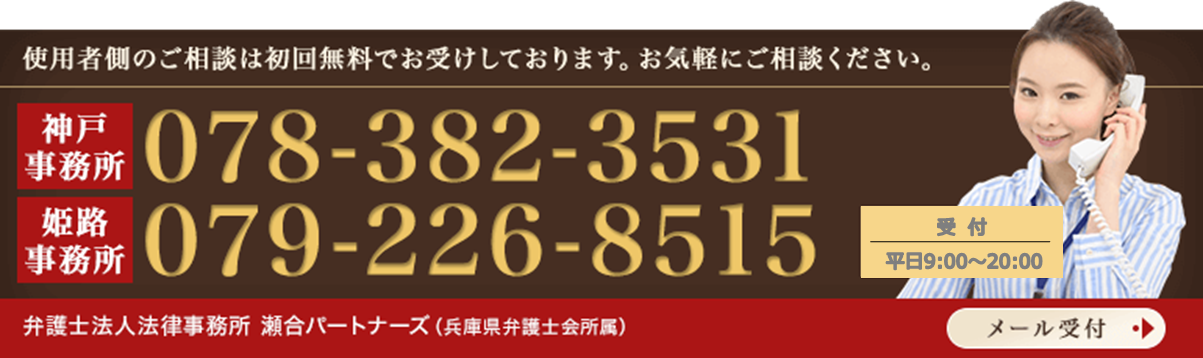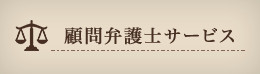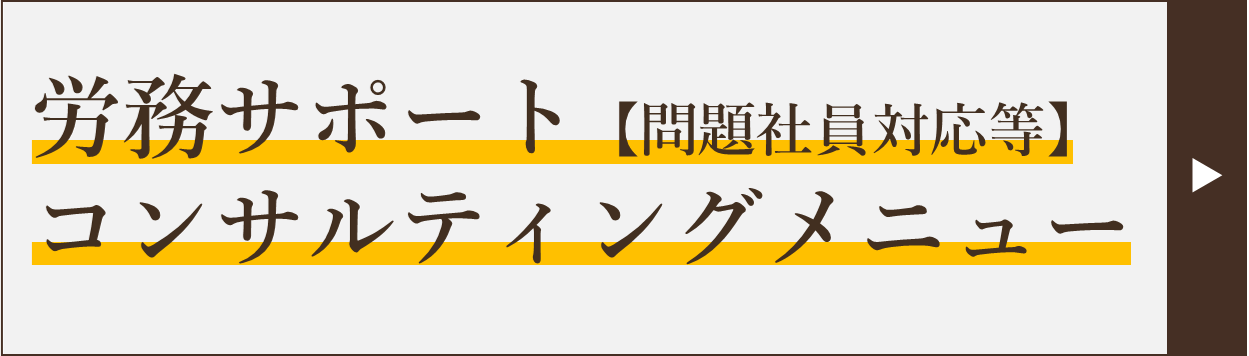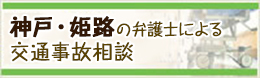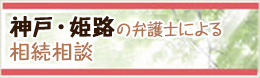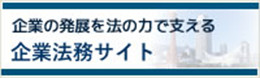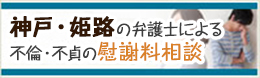「2025年6月施行の熱中症対策義務化で事業者が知っておくべき法改正と対応策について弁護士が解説」
目次
1. 熱中症による労災が深刻化…改正された理由と背景
(1)近年増加する熱中症による労働災害
近年、猛暑や異常気象の影響もあって、熱中症による労働災害が増加しています。特に日本の夏は気温が高く湿度も高いため、屋外での炎天下作業や高温の工場内での作業が多い業種において、熱中症のリスクが高まっています。厚生労働省のデータによると、熱中症による労災認定件数は年々増加傾向にあり、最悪の場合、死に至るケースも報告されています。そのため、企業における熱中症予防対策の重要性が社会問題として注目されるようになりました。
(2)労働安全衛生規則が改正された理由
これらの背景を受けて、2025年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、事業者に熱中症対策義務が新たに課されます。改正の狙いは、労働者の健康被害を未然に防ぐための具体的かつ実効的な対策を義務化することにあります。従来は努力義務として推奨されていた対策も、法的義務に格上げされる形です。企業は、この改正に対応し、体制の整備や教育を行う必要があります。
2. 室内作業でも安心できない!誰にでも起こりうるリスク
(1)屋外だけでなく屋内・軽作業も危険
熱中症の危険は屋外に限りません。工場や倉庫の中での作業であっても、十分な空調設備がない場合や密閉空間で熱がこもりやすい場合がありますので、発症リスクが高まります。また、軽作業であっても、高温多湿の環境で働くと体温調節が追いつかず熱中症を引き起こすことがあります。つまり、どのような環境や作業内容であっても油断は禁物なのです。
(2)認識不足が事故を招く典型パターン
熱中症は初期症状である頭痛や倦怠感を本人や周囲が見過ごし、適切な処置がなされなかった結果、重症化するケースが多々あります。また、「自分は大丈夫」という過信や、熱中症のリスク管理が徹底されていないことが原因で事故に至ることもあります。これを防ぐためには、事業者側の主体的な介入、早期発見体制の構築、従業員教育の充実が不可欠です。
3. 2025年6月施行の法改正によって企業に課される3つの義務
2025年6月から施行される改正労働安全衛生規則では、事業者に以下の3つの熱中症対策義務を課しています。
(1)異常の早期発見と報告体制の整備
現場において労働者の体調異常を早期に察知する体制を整備しなければなりません。具体的には、適切な温湿度の測定と体調チェック方法の設定、異変があれば速やかに報告・共有するシステムを構築する必要があります。これにより病状の悪化を防ぎ、速やかな対応が可能となります。
(2)対応措置の作成と従業員への周知
熱中症が発生した際の対応措置を明文化し、全従業員に対して周知徹底させることが求められます。例えば、症状の程度に応じた応急処置方法や医療機関への連絡体制、作業の中断基準等をマニュアル化します。従業員全員が緊急時に適切に動ける体制の確立が重要です。
また、作業環境を熱中症が起こりにくいように整備する必要があります。例えば、屋外の高温多湿作業場所においては簡易な屋根等を設けることや、近隣に冷房を備えた休憩場所や日陰等の涼しい休憩場所を設けることなどです。
(3)熱中症の予防教育の実施
労働者に対して熱中症のリスクや予防方法について定期的な教育・訓練を実施し、意識向上を図ることが義務付けられました。水分補給の重要性や危険なサインの見分け方、環境への対処法などを分かりやすく伝えることが必要です。
4. 義務違反による罰則と企業の責任とリスク
(1)安衛法違反に該当する場合の罰則内容
改正規則に基づく熱中症対策義務に違反すると、労働安全衛生法違反となり、罰則(罰金刑など)が科せられる可能性があります。また、行政指導や事業停止命令といった厳しい措置が取られるリスクもあります。これにより企業は経済的損失だけでなく社会的信用を大きく失うことになります。
(2)安全配慮義務との関係と判例上の責任
企業は労働者に対して安全配慮義務を負っており、熱中症対策を怠ることはこの安全配慮義務に違反することとなります。過去の判例でも、熱中症発症に対する企業の安全配慮義務違反が認められ、損害賠償責任が問われたケースがあります。企業としては、常日頃から具体的なリスク対策を講じていることが重要です。
5. 今すぐできる熱中症対策
事業者がすぐに取り組むべき具体的な熱中症対策は以下のとおりです。
(1)作業環境の温湿度管理(WBGT測定)
WBGT(湿球黒球温度)を用いた温湿度測定を定期的に行い、作業環境の状況を把握します。WBGT基準値とは、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のことをいい、この値が高い場合は作業中止や軽減措置を検討し、リスクをコントロールします。
今回、義務化の対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。
(2)作業時間・休憩の見直しと徹底
暑い時間帯の作業時間短縮や、こまめに休憩を取ることを制度化し、体力の消耗を防ぎます。また、シフト調整で暑さの厳しい時間帯の作業を少なくする工夫も効果的です。
(3)水分・塩分補給ルールの整備
熱中症予防の基本となる水分と塩分の適切な補給をルール化し、従業員に周知します。特に塩分補給は発汗によるミネラルの喪失を補うため重要です。
(4)空調・冷却機器の導入
作業場所に屋根、空調設備や冷却ファンを設置することは、作業環境の改善に直結します。携帯型冷却装置や冷却ベストの活用も推奨されます。
(5)従業員教育・注意喚起の継続
熱中症の兆候や予防方法について定期的な研修やポスター掲示などで注意喚起をし、労働者の意識を高め続けることが長期的な事故防止につながります。
6. 特に注意すべき業種
(1)建設業:炎天下での作業が多い
建設業は屋外作業が中心であり、特に直射日光下での作業が熱中症リスクを高めています。遮蔽物の設置や作業タイミングの調整によりリスク低減が必要です。
(2)製造業:高温機械周辺での作業リスク
工場内の高温機械付近での作業や密閉空間で熱がこもる作業は熱中症のリスクが高く、空調管理のほか作業方法の見直しが不可欠です。
(3)農業・物流:水分補給のタイミングが限られる現場
農作業や物流では、作業現場の広範さや屋外での連続作業により水分補給タイミングが限られることも多く、適切な管理と支援が求められます。
7.法改正を踏まえた早めの対応と専門家への相談のすすめ
2025年6月から義務化される熱中症対策を十分に講じない場合、企業は多大なリスクを抱えることとなります。労働者の安全を守ることは企業の社会的責任であるとともに、経営リスクの軽減にもつながるため、早期に対応されることをお勧めします。
しかし、具体的な対応策の策定や社内体制の構築は容易ではありません。対応策を考えたが十分だろうか、そもそも何から始めればよいのかわからない等でお困りの場合には、企業法務に詳しい弁護士へ早めにご相談ください。弁護士であれば、法改正についての最新情報の提供だけでなく、リスクマネジメントや労働安全衛生体制の構築を通じて、企業が安心して業務を継続できるよう適切なアドバイスを行うことが可能です。
熱中症事故は単なる労働災害にとどまらず、企業の信用問題や法的責任につながる重大事項です。お困りの際には、お気軽に当弁護士事務所までお問い合わせください。
以 上