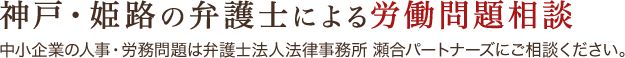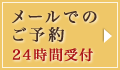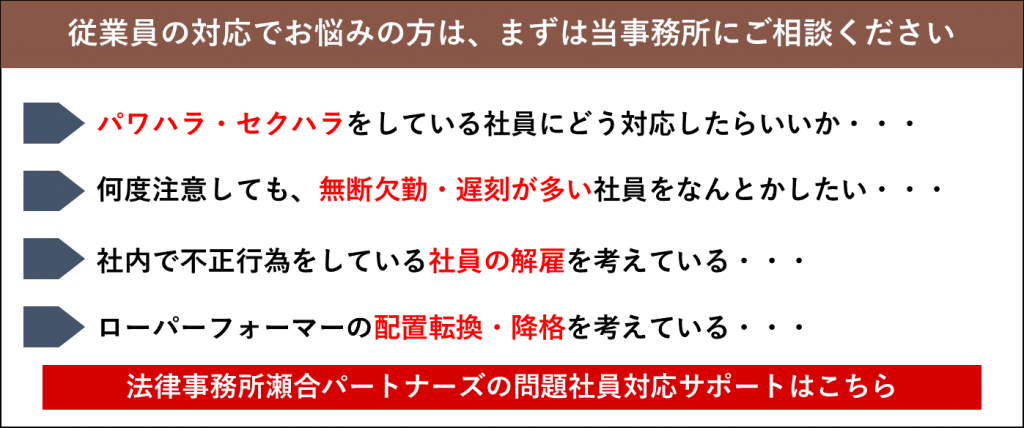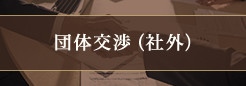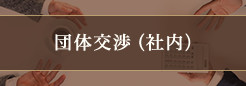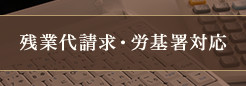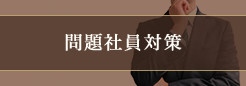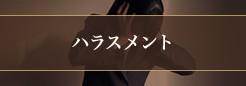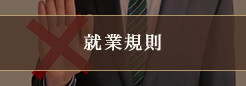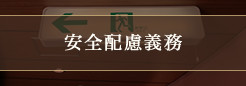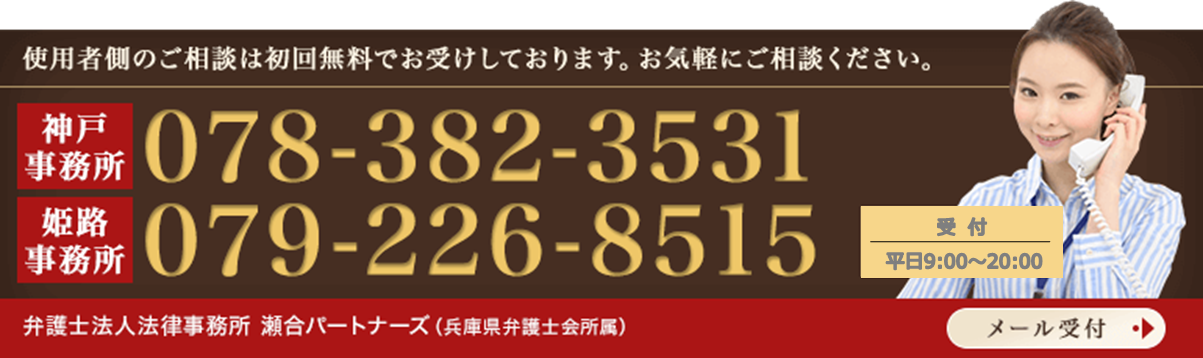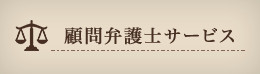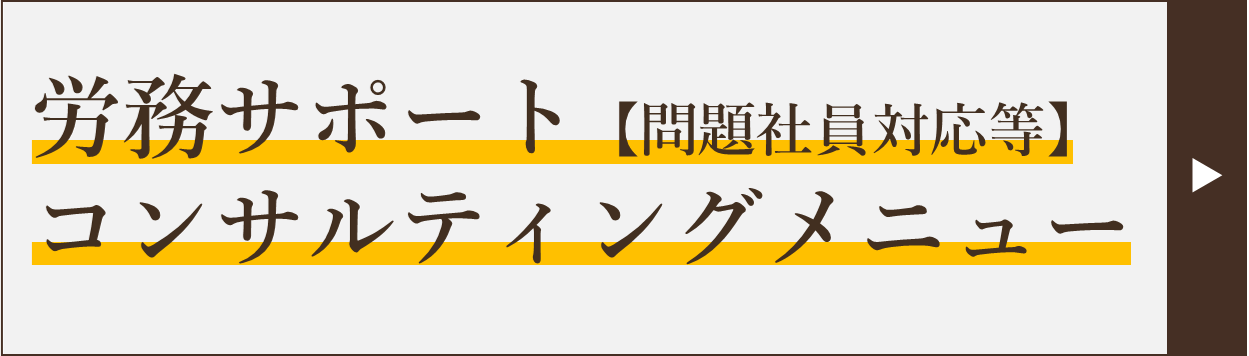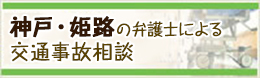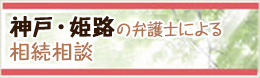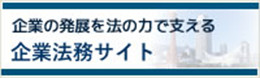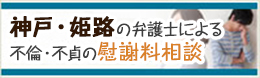従業員による企業秘密持ち出しへの対処法
1 なぜ企業秘密の持ち出しが問題となるのか
企業秘密には、顧客リスト、技術情報、価格設定、営業ノウハウなど、企業の競争力の源泉となる情報が含まれます。これらが従業員によって不正に持ち出され、特に同業他社へ流出した場合、顧客の奪取や売上の減少などの経済的損害が生じかねません。
さらに、企業秘密の漏洩は社内だけの問題ではありません。情報管理体制が不十分だと見なされ、株主・取引先・投資家からの信頼を損なうほか、個人情報保護法上の安全管理義務違反に問われる可能性もあります。
つまり、企業秘密の持ち出しは、経済的損失・法的責任・信用失墜という三重のリスクを企業にもたらすのです。
2 持ち出し発覚時の初動対応
不正な情報持ち出しが疑われた場合、最初の対応が極めて重要です。まずは以下のステップを迅速に実施します。
• 持ち出された情報の特定(何が・どこまで流出したか)
• 証拠の確保(アクセスログ、USB使用履歴、メール送信記録など)
• 従業員へのヒアリング(動機や経緯の確認)
• 関係部門・弁護士との連携(調査と法的対応の準備)
特に注意すべきは、流出情報の回収です。一度外部に出た情報の機密性を元に戻すことは困難です。そのため、速やかに削除・返還を求めることが重要になります。
3 法的措置と損害賠償請求
不正な持ち出しが明らかになった場合、企業は従業員に対し以下の民事上の責任を追及できます。
①債務不履行に基づく損害賠償(民法415条)
従業員は、労働契約に付随する秘密保持義務や就業規則・契約書に基づく義務を負っており、違反すれば損害賠償請求が可能です。
②不法行為に基づく損害賠償(民法709条)
漏洩により会社の財産権・信用が侵害された場合、民法709条に基づき損害賠償請求することもできます。
また、漏洩の重大性や悪質性に応じて、懲戒解雇や普通解雇も検討する必要があるでしょう。懲戒処分が有効とされるかどうかは、漏洩の影響、情報の重要性、従業員の行為態様、会社の管理体制などを総合的に判断して決まります。
4 刑事告訴も視野に入れた対応
悪質な漏洩の場合は、民事だけでなく刑事責任の追及も可能です。
① 不正競争防止法違反
営業秘密を不正に使用・開示した場合、同法に基づき10年以下の懲役または2,000万円以下の罰金が科されることがあります。営業秘密として保護されるには、以下の3要件を満たす必要があります:
1. 秘密管理性(アクセス制限・「社外秘」表示など)
2. 非公知性(一般に知られていないこと)
3. 有用性(事業活動に有益であること)
このうち「秘密管理性」が最も争点になりやすいため、日頃からの管理体制が極めて重要です。
②窃盗罪・業務上横領罪
紙媒体などの「有体物」を持ち出した場合には、刑法上の窃盗罪や業務上横領罪が適用される可能性がありますが、データのような無体物には通常適用されません。この点でも不正競争防止法が重要な法的手段となります。
5 再発防止策と秘密保持体制の強化
従業員による情報流出を防ぐには、以下のような日常的な体制整備が欠かせません。
①規程と契約によるルール化
• 就業規則に秘密保持義務を明記
• 情報管理規程で対象範囲・管理方法を具体化
• 秘密保持契約(NDA)の締結と運用
就業規則に明記がない場合でも、労働契約上の付随義務として追及できますが、実務上は明文化しておくことでトラブル時の証明が容易になります。
②技術的・運用的対策
• 機密情報へのアクセス制限・ログ管理
• USB・クラウドの利用制限やモニタリング
• 退職時チェックリストの徹底(端末回収・アクセス遮断)
③ 教育と企業文化の醸成
• 定期的な情報セキュリティ研修
• 社内ポリシーの周知と意識向上
従業員一人ひとりに秘密保持の重要性を理解させることが、何よりの防止策となるのです。
6 まとめ
従業員による企業秘密の持ち出しは、企業の収益・信頼・法的責任に深刻な影響を及ぼします。発覚時には迅速な調査・証拠保全を行い、損害賠償や刑事告訴も視野に入れた対応が求められます。
また、トラブルを未然に防ぐためには、社内規程の整備、技術的対策、従業員教育の三本柱による秘密保持体制の強化が不可欠です。企業の知的資産を守るためにも、平時からの備えを怠らないことが、現代の情報管理における基本姿勢といえるでしょう。
以上