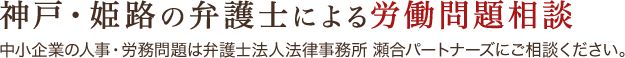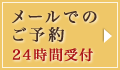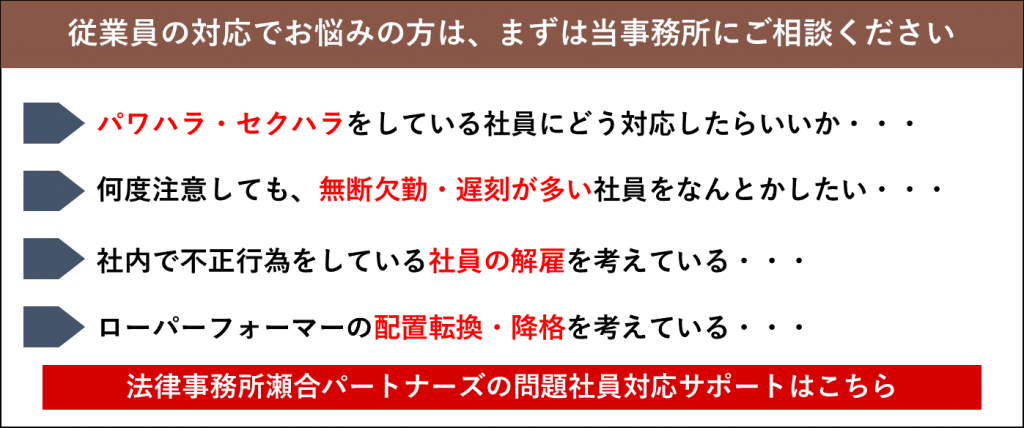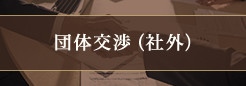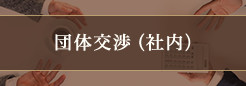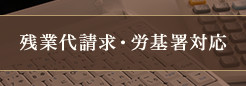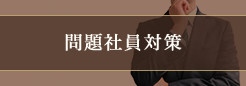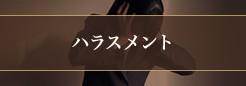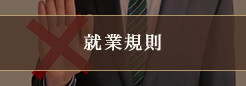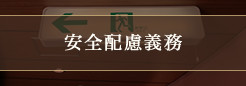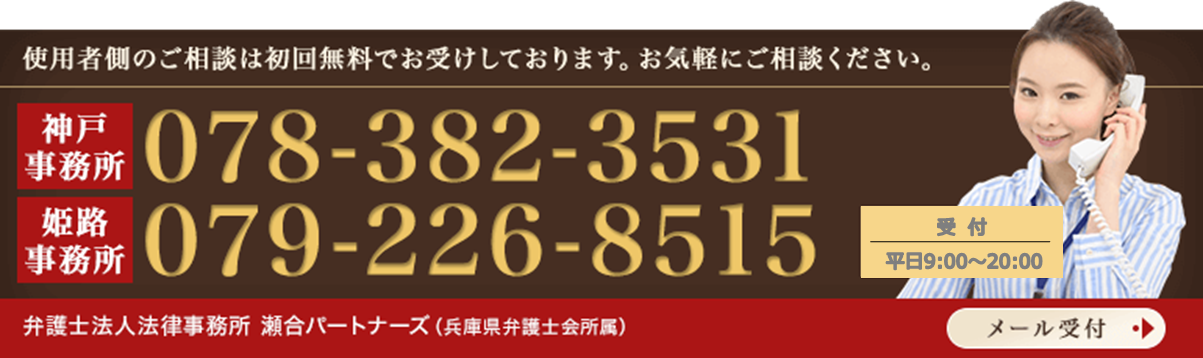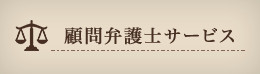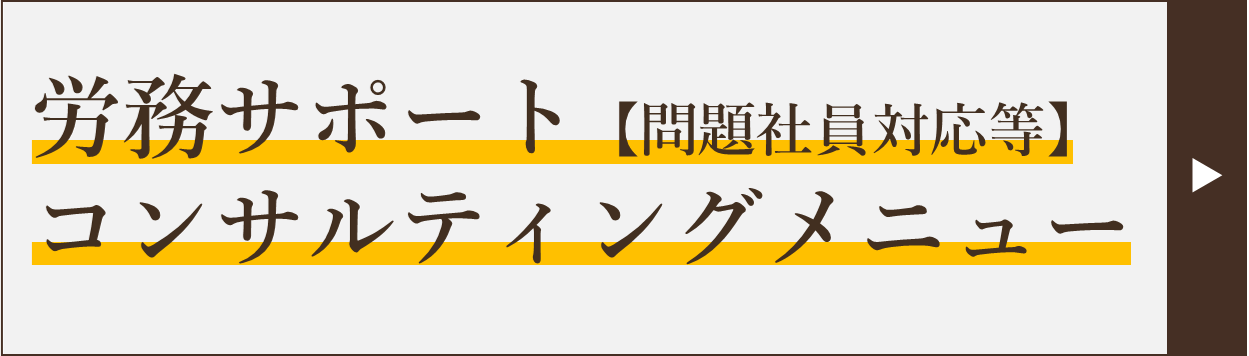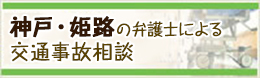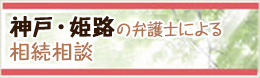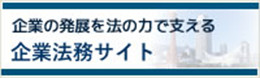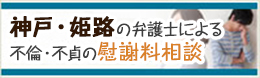IT業界の偽装請負問題について弁護士が解説
昨今、IT業界で問題視されている「偽装請負」。表面的には業務委託や請負契約を結びながら、実態は違法な労働者派遣とみなされるこの契約形態は、コンプライアンス違反として企業に深刻なリスクをもたらします。
本記事では、偽装請負の仕組みから、企業が取るべき具体的な対策までを分かりやすく解説します。
目次
1 偽装請負の基本的な仕組み
偽装請負とは、形式上は業務委託契約や請負契約となっているにもかかわらず、実態としては発注元が受注側の雇用する労働者に対し、直接的に業務の指揮命令を行ったり、業務遂行方法を細かく指示したりする状態のことを指します。
請負契約は、仕事の完成を目的とし、受注者が自己の責任と裁量で業務を遂行するのが原則です。一方で、労働者派遣契約は、派遣元が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令下で働かせる契約です。
偽装請負は、この二つの契約の「良いとこ取り」をしようとする行為です。企業は、業務委託という名目で人件費を抑えつつ、派遣社員のように自社の都合で労働者を自由に使えると考えてしまいがちです。しかし、これは後述の通り、職業安定法や労働者派遣法に違反する違法行為です。
2 請負契約と労働者派遣契約の違い
請負契約と労働者派遣契約の最も重要な違いは、「指揮命令権の所在」です。
労働者派遣契約の場合、労働者に対する指揮命令権は派遣先(発注元)にあります。具体的には、派遣先の担当者が派遣先で働く労働者に対して、直接業務の指示や勤怠管理を行います。
これに対し、請負契約は、単に仕事の完成を目的とする契約ですので、労働者に対する指揮命令権は受注側に属したままです。
請負契約を結んでいるにもかかわらず(=本来は受注側が指揮命令権を持っているはずなのに)、発注元が業務上の指示を行い、労働者を直接指揮命令している場合、それは実質的には労働者派遣に該当します。
3 偽装請負が発生しやすいIT業界の背景
IT業界で偽装請負が発生しやすい理由としては、主に以下のような点が挙げられます。
・プロジェクトの短期化・流動化
迅速な開発が求められるアジャイル開発などが主流となり、プロジェクトの期間が短く、人員の入れ替わりが激しい。
・専門的な人材の不足
AI、データサイエンス、クラウドなどの専門知識を持つエンジニアが慢性的に不足しており、外部人材への依存度が高い。
・SES(システムエンジニアリングサービス)契約の多用
エンジニアの技術力を提供するSES契約は、業務委託契約として締結されることが多いが、実態として指揮命令が発生しやすいため、偽装請負のリスクを内包している。
これらの状況から、発注元が「この人がいないとプロジェクトが進まない」という状況に陥り、直接的な指示を出してしまうケースが後を絶ちません。
4 違反が発覚した場合のペナルティ
偽装請負を行った場合、以下のような厳しいペナルティが科されます。
・労働者派遣法違反
偽装請負が無許可での労働者派遣に該当する場合、受注側の事業者には、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。また、行政指導や勧告の対象にもなり、最悪の場合、企業名が公表されてしまうおそれもあります。
・職業安定法違反
偽装請負が労働者供給に該当する場合、受注側・発注元双方の事業主に、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。
・労働基準法違反
偽装請負が中間搾取に該当する場合、受注側の事業主に、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます。
このように偽装請負には多大なるリスクがあり、発覚した場合には事業継続そのものが脅かされる事態に発展しかねません。
5 偽装請負を避けるための実務上の対策
偽装請負のリスクを回避するためには、日々の業務運用において、以下の点を徹底することが不可欠です。
・明確な契約書の作成
契約書に業務の完成義務と責任範囲を明確に記載し、指揮命令権は受注側にあることを明記します。
・発注担当者に対する教育
発注元の担当者に対し、受注側が雇用する労働者へ直接指示を出さないこと、業務遂行方法への口出しをしないことなどを徹底的に教育します。
・進捗管理の方法を工夫する
進捗確認は、作業報告書や成果物を通じて行い、発注元が具体的な業務プロセスに踏み込まないようにします。
・連絡窓口の一本化
発注元からの連絡は、受注側の責任者を窓口とし、個々の労働者への直接的な連絡を禁止します。
これらの対策は、契約の形式・名称だけでなく、実態としても「請負」であることを証明するために重要です。
6 IT企業が取るべきコンプライアンス対応
偽装請負を根絶させ、健全な事業活動を行うためには、企業全体でのコンプライアンス意識向上が欠かせません。
・社内規程の整備
業務委託契約における指揮命令権の禁止を明文化した社内規程を作成し、全従業員に周知します。
・定期的な研修の実施
営業担当者やプロジェクトマネージャーなど、外部人材と関わる機会の多い社員向けに、偽装請負に関する法務研修を定期的に実施します。
・法務部門との連携
新規契約を締結する際には、必ず法務部門や顧問弁護士と連携し、契約内容が適切であるかを確認します。
・外部監査の導入
定期的に外部の専門家(弁護士など)による監査を受け、契約の実態が法的に問題ないかチェックする体制を構築することも有効です。
特にSES企業においては、自社のエンジニアが発注元から不当な指揮命令を受けていないか、定期的にヒアリングを行うなどの配慮が求められます。
7 まとめ
IT業界における偽装請負は、企業にとって多大なリスクを孕む深刻な問題です。しかし、適切な知識と対策を講じることで、これらのリスクは回避できます。
大切なのは、形式だけでなく実態として請負契約の原則を守ることです。発注元、受注側の双方が、仕事の完成を目的とし、発注元は指揮命令権を持たないという意識を共有することが、健全なビジネスを継続する上で不可欠となります。
偽装請負の疑いがある、契約内容について不安があるなど、お困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。貴社の事業がコンプライアンスを遵守し、健全に発展していくために、専門家として全力でサポートいたします。