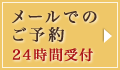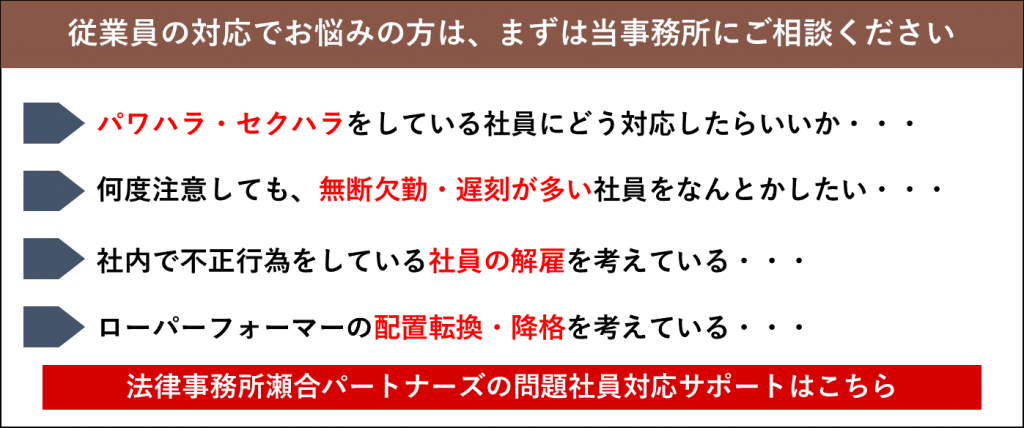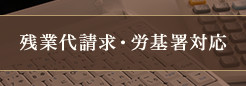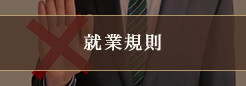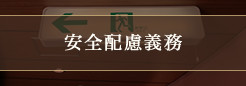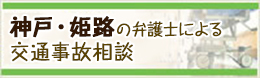Q.営業秘密を漏洩する社員への対応方法
テーマ:営業秘密を漏洩する社員への対応方法
質問
会社の顧客名簿等の営業秘密をライバル会社へ売って、お小遣いを稼いでいる社員がいることが判明しました。
会社としては、どのように対応すればよいでしょうか?
回答
1.労働者の秘密保持義務(民事上の責任・損害賠償請求)
労働者には秘密保持義務がありますので、同義務違反として損害賠償を請求することが考えられます。秘密保持義務の根拠は以下のとおりです。
まず、①就業規則に規程する(「従業員は、在職中のみならず退職後においても、会社が業務上秘密としている事項について、漏えい・開示・自ら使用してはならない」)ことが考えられます。
次に、②労働契約の付随的義務の一つとして認められます。この点を認めた判例として古河鉱業事件(東京高判昭和55.2.18)があります(「労働者は労働契約に基づく付随的義務として、信義則上、使用者の利益をことさらに害するような行為を避けるべき義務を負うが、その一つとして使用者の業務上の秘密を洩らさないとの義務を負うものと解される」)。
また、③秘密保持誓約書(「私は、在職中に従事した貴社が秘密としている事項について、退職後においても、これを他に漏えい・開示せず、自ら使用しないことを誓約します」)をとることも考えられます。
実務的には、①就業規則に規程することに加えて、労働者に秘密を保持する義務があることを自覚させる意味でも、③秘密保持誓約書をとることをお勧めします。
秘密保持誓約書のとるタイミングとしては、できれば、入社時と退社時の双方でとることがのぞましいでしょう。
退社時にあわてて同誓約書をとろうとしても、難しいところがありますので、一番取得しやすい入社時に一度取得しておき、退社時に再度、念を押す意味でも同誓約書をとるようにするとよいです。
なお、データの持ち出しにより、売上が減少する損害を被ったとしても、損害や因果関係が否定されるなど、立証が困難なおそれが高いです。
そこで、退職時の守秘義務誓約書において、損害賠償額の予定を定めておくことをお勧めします。
なお、在職中の守秘義務誓約書では、損害賠償額の予定は労働基準法16条に違反し、できませんのでご注意ください。
2.懲戒処分
もちろん就業規則に秘密保持義務違反等を懲戒事由として規程しておけば、懲処分の対象となります(「業務上の秘密を漏えいした」「故意または過失により会社に損害を与えた」)。
どの程度の懲戒処分が相当かですが、下記の3つの項目を考慮して判断すべきでしょう。
①結果の重大性(営業秘密の重要性、秘密漏えいによる会社の被る損害の程度等)、
②行為の態様(秘密漏えいの相手方、漏えいの方法、漏えいによる対価取得の有無等、営業秘密漏えいに至った動機、目的等)、
③その他情状(本人の反省の程度等)
ご相談のように、顧客名簿等の営業秘密が会社にとって極めて重要、他社に売却されたことにより会社が被る損害が重大であるような場合には、懲戒解雇を選択することもあり得ます。
3.不正競争防止法との関係
不正競争防止法に基づいて、差止め、損害賠償請求、さらに刑事責任を追及することも考えられます。その場合、保護の対象である「営業秘密」に該当することが必要となります。
「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争2条6項)をいい、①秘密管理性、②有用性、③
非公知性が要件となります。
なお、①に関しては、「マル秘」の記載をすることや、取扱者を限定して管理することがポイントとなります。
また、秘密保持は漏洩した場合の損害が大きいですので、事前予防として、事前の検知措置(アクセスしたことを知らせるシステム等)をとっておくことが適切です。
4.ライバル会社への対応
①まずは情報収集に努めます。
②次に、当該社員とライバル会社との接点が判明する等した場合、書面等により秘密情報の利用を中止する旨の申入れをすることが考えられます。
③ライバル会社が、当該社員と共同して秘密情報を違法に入手していたことが判明した場合には、民法709条に基づく損害賠償を請求することが考えられます。
④不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する場合、差止請求や刑事告訴(企業に対する罰則は5億円以下の罰金)も可能です。
このように、収集できた情報によっては、ライバル会社への対抗手段も必要となる場合があるでしょう。
問題社員への対応についてお困りの経営者の方は、ぜひ一度労務問題に詳しい弁護士にご相談ください。
企業は、日々、労働組合からの団体交渉の申し入れ、元従業員からの残業代請求、ハラスメント(パワハラ、セクハラ)の訴え、解雇に伴うトラブルなど、あらゆる課題を抱えています。誰にも相談できずに悩まれていらっしゃる経営者の皆様も多いと思いますが、まずは一度、労働問題に強い弁護士にご相談ください。